IN/OUT (2025.7.6)
全く、梅雨らしい雰囲気が無いまま、猛暑が続いています。もう、異常気象が通常という状態ですね。
 最近のIN
最近のIN
”Sinners” (25.7.4)
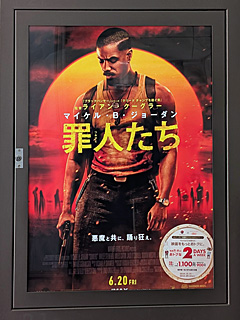 "Black Panther"のRyan Coogler監督の新作を観てきた。邦題は「罪人たち」。
"Black Panther"のRyan Coogler監督の新作を観てきた。邦題は「罪人たち」。
舞台は、禁酒法下の1932年、米国南部の田舎町。シカゴで金を(おそらくは、汚い稼業で)稼いで地元に帰ってきた双子の兄弟(Michael B. Jordanが二役で演じている)が、白人地主から土地と建物を買い取り、アルコールも振る舞うダンスホールを開店する。しかし、そのオープンの日、招かれざる客がやってくる。というお話。
映画の前半は、双子が、かつての仲間や、ブルーズ・ミュージシャンを志す甥っ子などを巻き込んで、ダンスホールの開店準備を進める様子が、テンポ良く、登場人物達の紹介を過不足なく織り込みながら描かれる。そして、後半は一転して、ヴァンパイアを相手にしたホラー活劇になる。”From Dusk Till Dawn”的な展開だ。ちょっと、後半の主人公達の行動が、無手勝流過ぎる感じはあるが。
その一方で、これは優れた音楽映画でもある。甥っ子が演奏するブルーズも、彼が憧れる女性歌手のパンチのある歌も、ヴァンパイア達が踊るアイリッシュ・フォーク(!)も、どれもクオリティの高いパフォーマンスだ。
特に、優れたミュージシャンによる演奏が、時空を超え、過去と未来を結び、様々な民族文化をつなぐというコンセプトを可視化したシーンが素晴らしい。まさに、映画ならではのマジックだ。もっとも、これが、結果的にはヴァンパイアを呼び寄せてしまうのだが(当時、ブルーズは良識派の人からは「悪魔の音楽」と呼ばれていた)。
映画のオチ的な場面に、伝説的ブルーズ・ミュージシャン Buddy Guy(1936年生まれ)が顔を出すのも、気が利いていて、一筋縄では行かないが、非常にエキサイティングな映画だ。
”F1: The Movie” (25.7.5)
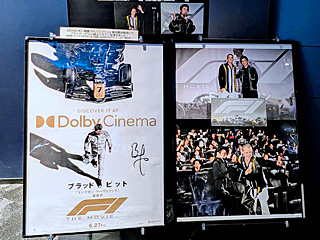 Brad Pitt主演の新作を観てきた。監督は、"Top Gun: Maverick"のJoseph Kosinski。邦題は「F1™/エフワン」。
Brad Pitt主演の新作を観てきた。監督は、"Top Gun: Maverick"のJoseph Kosinski。邦題は「F1™/エフワン」。
Brad Pittが演じるのは、30年前、Ayrton SennaやAlain Prostと渡り合っていた元F1ドライバー。事故でF1から遠ざかり、今では車上生活をしながら、あちこちのレースに出ているのだが、低迷しているF1チームの代表である旧友に乞われ、彼のチームに復帰する。年は取っても滅法早く、老獪な(ルール違反すれすれの)策も弄し、徐々にチームの成績を上向かせていく。そして…。というお話。
製作陣は、”Top Gun: Maverick”の成功で味を占めたのか、物語の構造はとても良く似ている。一匹狼のベテランが、初めはチームの面々から白眼視され、優秀だが生意気な若手と衝突しながらも、その圧倒的実力で信頼を勝ち得、チームをまとめ、無謀と思えた勝利に向かう。清々しいほど何のてらいも無い、王道の筋立てだ。そして、観客が喜びそうな「カッコ良いブラピ」を、出し惜しみ無く見せてくれる。
その一方で、個人ではなく、チーム戦としてのF1をしっかり見せることで、より、エモーショナルな熱さを高めているところも上手い。チームのテクニカルディレクター役のKerry Condonも印象的だと思って調べたら、あの重い”The Banshees of Inisherin(イニシェリン島の精霊)”に出ていた人だった。幅の広い俳優だ!
物語としては、古風とも言える映画だが、実際のレーシング・カーと、このためにソニーが新たに開発したカメラを用いた映像が圧倒的で、155分間の長尺をまったく飽きること無く、レースの世界に没入できる。
Hans Zimmerの音楽も、冒頭に流れるLed Zeppelinの「Whole Lotta Love」も、カッコ良し。まぁ、我々の年代だと、せめて鈴鹿のレース・シーンでは、THE SQUAREの「TRUTH」も流してほしかったところだが。
”Fremont” (25.7.6)
 米国カリフォルニア州の都市フリーモント(Fremont)に暮らすアフガニスタン出身の女性を主人公にした映画を観てきた。Fremontは、米国で最もアフガニスタン系住民が多い地域なのだ。邦題は「フォーチュンクッキー」
米国カリフォルニア州の都市フリーモント(Fremont)に暮らすアフガニスタン出身の女性を主人公にした映画を観てきた。Fremontは、米国で最もアフガニスタン系住民が多い地域なのだ。邦題は「フォーチュンクッキー」
邦題の通り、主人公はフォーチュンクッキー工場に勤めている。元は、アフガニスタンで米軍の通訳として働いていたが、米国に移住してきた彼女は、不眠症に悩まされながら、単調な日々を送っている。クッキーの中に入れるメッセージを書く事を任された彼女は、ふと思いついて、そこに個人的メッセージを忍ばせたのだが…
米国の中華料理店でお馴染みの、フォーチューンクッキー。おみくじとは違う、微妙に訳が分かるような、分からないような、あの独特の言葉(米国で生活していたとき、とても印象的だった事の一つだ)は、こんな感じで作られていたのかも、と思ってしまった。現状打破のために彼女が取った、ちょっと思い切った行動が、期待したのとは全く違う角度から、でも、確実に彼女を前に進めることに導く。というのが、いかにも、フォーチュンクッキーのお告げっぽい。
モノクロ映像のオフビートな展開だが、芸術気取りじゃ無いのが好ましい。その淡々とした描写の中に、主人公と、彼女を取り巻く人々=アフガニスタン系のご近所さん、工場の中国人経営者夫妻、Jack Londonの”White Fang”に心酔する精神分析医、自動車修理工、皆の人柄が立ち上がってくる。
なお、主演のAnaita Wali Zadaは、これが映画初出演。アフガニスタンでテレビ番組の司会者・ジャーナリストとして活躍していたが、タリバンの標的となり、米国へ移住したということで、劇中の主人公と同様の境遇。彼女の自然体の表情も見どころだ。
全く派手さはなく、眠くなるシーンも多いのに、見終わったら、なんだか温かい物が残る。主題歌的に使われているVashti Bunyanの「Just Another Diamond Day」の雰囲気そのままの映画だ。
なお、鹿にまつわるオチも、"deer"という言葉が "a male who appears to get girls, but in reality doesn't"という意味で用いられることがあるということを映画の後で調べて、なるほど、合点! 工場経営者の奥様、お人が悪い!
”HIKARI 2025 INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL” @ 渋谷ストリームホール (25.7.6)
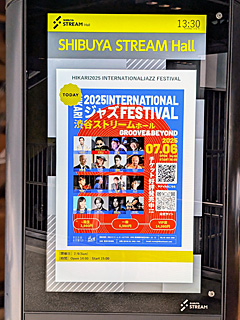 寺井尚子カルテットと川口千里バンドを目当てに、渋谷ストリームホールで開催されたジャズ・フェスティバルを観に行ってきた。
寺井尚子カルテットと川口千里バンドを目当てに、渋谷ストリームホールで開催されたジャズ・フェスティバルを観に行ってきた。
会場の渋谷ストリームホールは、東急東横線の旧渋谷駅の跡地辺りの再開発で出来た渋谷ストリーム内にあり、JRの新南改札直結。渋谷の雑踏を歩かずに行けるのがありがたい。キャパは、スタンディングだと約500名。今日のような座席を置く形式だと、205席ほど。
チケットを取った後で知ったのだが、このイベントの主催は「東京光音楽塾」。2019年に開講した、留学生向けの音楽塾だ。日本の音楽大学や、その附属校、音楽専門学校の受験を目指す留学生を対象にしており、学生の殆どが中国人ということだ。
そのせいか、開場から客入れの段取りが極めて悪い。が、なんとか、前方中央の、比較的良い席を確保(自由席のイベント)。
最初の出演者は、Hikari All Star。日本人と中国人の混成バンド。東京光音楽塾で開催される月例のセッションに参加しているミュージシャン達ということで、このフェスを代表するメンバーと言えるだろう。
・李 暁川(トランペット)
・多田 誠司(アルト・サックス)
・岡崎 正典(テナー・サックス)
・關 家傑(ギター)
・道下 和彦(ギター)
・田中 裕士(ピアノ)
・紀 鵬(ベース)
・大坂 昌彦(ドラムス / バンドリーダー)
演奏されたのは、各メンバーのオリジナル作を5曲ほど。皆、それなりのキャリアを持つ人達なので、演奏技量は高い。が、何か、このバンドじゃなければ、というものは感じられなかった。普通に上手いジャズ・バンドという感じ。
20分間の休憩後、寺井尚子カルテットが登場。ヴァイオリンの寺井尚子の他
・北島 直樹(ピアノ)
・仲石 裕介(ベース)
・荒山 諒(ドラムス)
何度も観ているお馴染みのカルテットである。
1曲目「セルタオ」から、姐さん、飛ばしまくりという感じの演奏だ。申し訳ないが、Hikari All Starと比べると、4人とも、音の輪郭がくっきりした、圧倒的にエモーショナルな響き。流石である。「首の差で(”Por una cabeza”。映画”Scent of a Woman”で使われている)」、メンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64」、Ennio Morriconeの映画音楽(”The Mission”)「Gabriel's Oboe」、そして、北島直樹がこのカルテットのために書いた「過ぎ去りし日々(Those Foolish Days)」。どれも、名演。
そして、また20分間の休憩後、川口千里バンド。ドラムスの川口千里の他
・菰口 雄矢(ギター)
・友田 ジュン(キーボード)
・高橋 佳輝(ベース)
1月にBlues Alley Japanで観たときから、サックスは不在で、キーボードが代わっている。
冒頭から、怒濤の音圧で、「See You Much Later」、「In Three Ways」、「Longing Skyline」の三連打。中々流暢な中国語を交えた挨拶の後、菅沼孝三の「Winds」、「Tombo in 7/4」。自身のリーダー・バンドだけに、川口千里、叩きまくりである。そして、バックの演奏も的確。初めて観る友田ジュンも、好プレイだ。全曲、超絶、気持ち良し。
本人も、「前の二組と違い、唯一、スウィングしないバンドですが…。このままスウィング無しで突っ切ります!」と宣言し、最後は「FLUX CAPACITOR」と「Onyx」の大迫力の演奏で全編終了。川口千里のライヴ演奏を観る機会は、まぁまぁあるのだが、ビッグ・バンドの一番奥だったり、手前のメンバーの譜面台が邪魔になったりして、演奏する姿を視認するのが難しいことが多い。しかし、今回は、かなりの至近距離で、演奏中の楽しそうな表情もしっかり見ながら、その圧倒的手数を浴びることができ、大満足だ。
ということで、開演前の段取りで不安もあったのだが、始まってみれば、比較的小さな会場で寺井尚子姐さんと川口千里嬢のプレイを堪能でき、仕切りの悪さも無問題である。
この暑苦しさをさらに助長するような、参院選の選挙カーやら街頭演説。まだ7月前半なのに、不快指数Maxな今日この頃です。